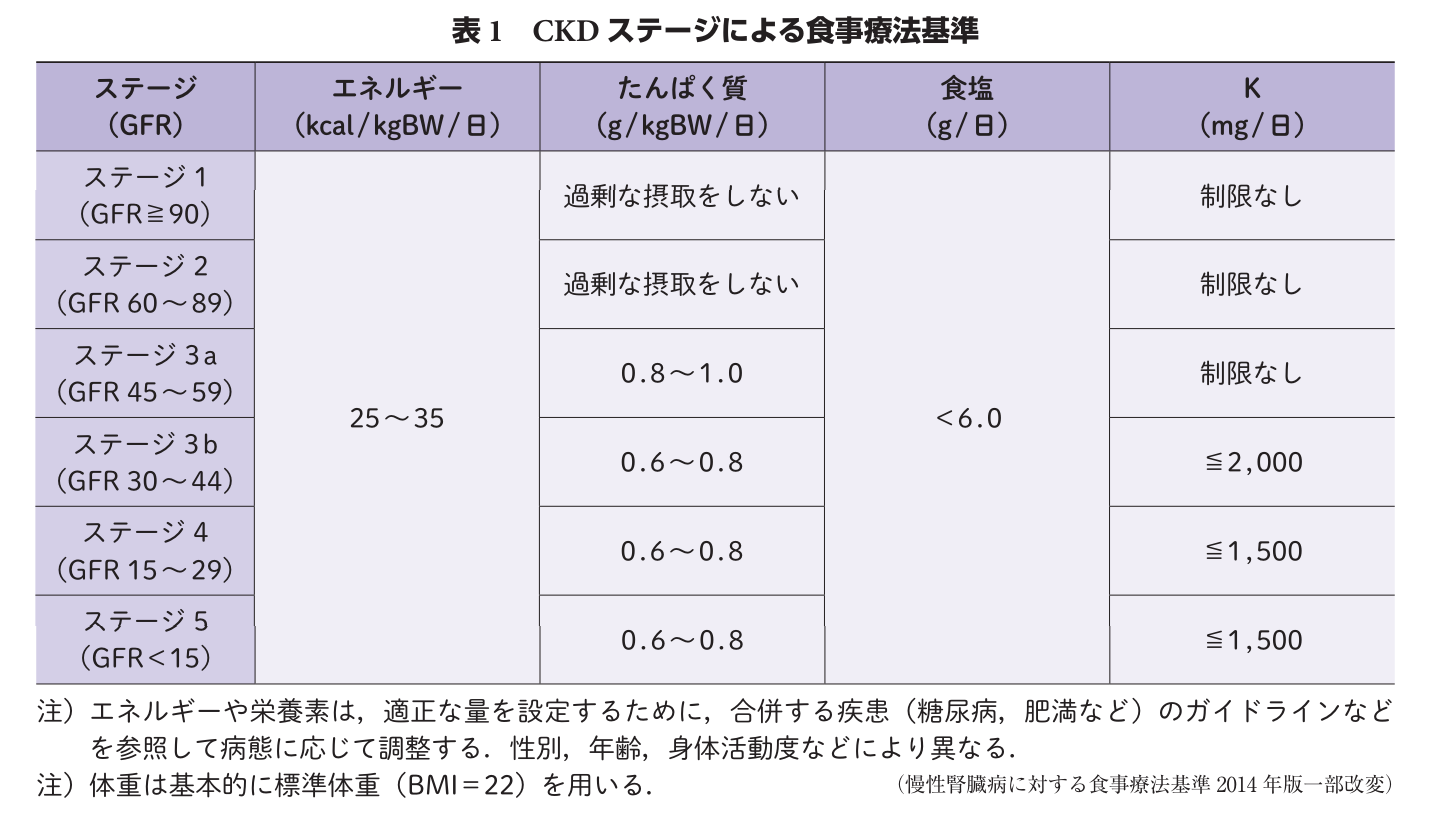慢性腎臓病の食事療法について
ページ内目次
腎臓病食とは、摂取カロリーを減らしたものではない
進行した慢性腎不全に対し、生活改善、食事療法、薬物療法など、行うべきことは多岐にわたります。初期の腎疾患を健診やかかりつけ医から指摘され、腎臓内科外来を初めて受診する患者さんの中には、予め「食事療法を始めてきた」という人も少なくなく、食事療法への関心の高さが伺えます。
しかし、その多くはカロリー制限をしたという、いわゆるダイエットであり、腎臓病に適した食事療法の中身がよく知られているとは言い難いのが実状です。もちろん、肥満は慢性腎臓病の危険因子であり、食べ過ぎ・太り過ぎの自覚のある方は、生活習慣病予防の観点からも、カロリー制限をするべきでしょう。しかし標準体重どおり、あるいはやせ形・小食の方が腎臓に良かれと思ってカロリー制限を行うことは、正しくありません。腎臓病食として押さえるべきポイントは、減塩とタンパク制限です。
しかし、その多くはカロリー制限をしたという、いわゆるダイエットであり、腎臓病に適した食事療法の中身がよく知られているとは言い難いのが実状です。もちろん、肥満は慢性腎臓病の危険因子であり、食べ過ぎ・太り過ぎの自覚のある方は、生活習慣病予防の観点からも、カロリー制限をするべきでしょう。しかし標準体重どおり、あるいはやせ形・小食の方が腎臓に良かれと思ってカロリー制限を行うことは、正しくありません。腎臓病食として押さえるべきポイントは、減塩とタンパク制限です。
もう少し具体的に…
食塩摂取量の目安は 3g/ 日以上 6g/ 日未満とされています。佃煮や漬物は、これまでの半分量にするなど、控えめにしましょう。汁物は、具だけ摂取し、汁をあまり飲まないようにしましょう。薄味が苦手な方は、お酢など、他の調味料に置き換えるように努めましょう。スーパーや通販サイトで「減塩しお」を見かけることがありますが、これは塩化ナトリウムを塩化カリウムに置き換えたものなので、初期の腎臓病なら大丈夫ですが、進行した腎不全ほかカリウム制限が必要な疾患の場合には適しません。
タンパクとは、肉、魚、大豆が代表的です。腎臓内科の診療では、動物性タンパクと植物性タンパクとを特段区別していません。タンパク制限とは、健常者よりもタンパク摂取を減らすことであり、決してタンパク摂取量をゼロにすることではありません。タンパク摂取量を減らしても、総カロリーを保つ必要があるため、相対的に炭水化物や脂質を増やすことになります。
よく「決して摂取してはいけない食材は何か」という質問を受けますが、実際はそのような極端な食材は皆無です。腎臓にあまり好ましくない食品であっても、通常の半分~ 3分の 1 など少量の摂取であれば許容されるものがほとんどであり、過度に腎臓病食の実践を恐れる必要はありません。
下のイラスト(天ぷら、ドリア、酢の物、フルーツポンチ)は、腎臓病食として比較的好ましい献立を例示しています。進行した腎不全の場合には、カリウム制限やリン制限、飲水制限も必要になる場合があります。また体格や他の持病によっても、行うべき食事療法の内容は人それぞれ異なります。詳しくは、腎臓内科受診や、管理栄養士による栄養指導を受けることをお勧めします。
よく「決して摂取してはいけない食材は何か」という質問を受けますが、実際はそのような極端な食材は皆無です。腎臓にあまり好ましくない食品であっても、通常の半分~ 3分の 1 など少量の摂取であれば許容されるものがほとんどであり、過度に腎臓病食の実践を恐れる必要はありません。
下のイラスト(天ぷら、ドリア、酢の物、フルーツポンチ)は、腎臓病食として比較的好ましい献立を例示しています。進行した腎不全の場合には、カリウム制限やリン制限、飲水制限も必要になる場合があります。また体格や他の持病によっても、行うべき食事療法の内容は人それぞれ異なります。詳しくは、腎臓内科受診や、管理栄養士による栄養指導を受けることをお勧めします。

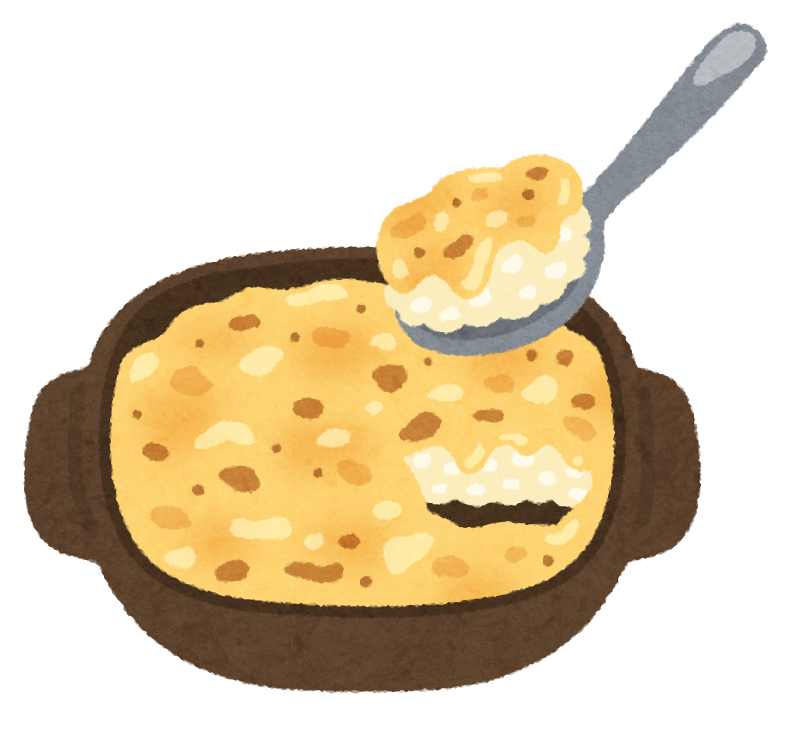


執筆医師
2023 年8月から着任しました。疑問点があればひとつひとつ解決していきましょう。ちなみに、辛い料理が大好物です。
腎臓内科 川勝祐太郎